時事逓信屋 PAGE 10
① 未来の水素マシーン(Hydrogen Generator) ② カメラ ③ 自転車 ④ 冤罪 part2 ⑤東京ドーム part2⑥お米騒動 ⑦AIと人間の決断 ⑧自動車の税金 ⑨透明な色(AIの見解) ⑩ 食品ロス(make-believe story)
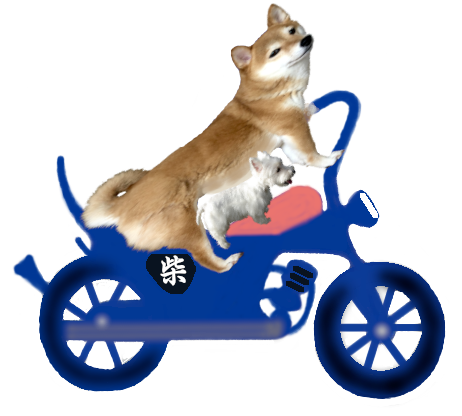
①未来の水素マシーン(Hydrogen Generator)
FUTURE STORY
水を硫酸ナトリウムで電気分解すると水素と酸素が発生する。と、言う事は水素と酸素が結合すると水になる訳で、その水は一度結合した水は、その後、酸素に触れても水は水のままである。水(H2O)→水素分子が2つと酸素原子1つで2H2+O2となり、化学反応の結果2対1の水は2対1+1のように更に結合する水は存在しない。つまり、自然界の法則は変えられないと言う事である。それらを踏まえて考えると、例えば水を製造するには自然界では、いとも簡単に作るけれど、人工で水を作るのは熱エネルギーを要する。それは水素も酸素も同じ事が言えて、物質の製造には熱エネルギーを要する事が言える。
そこで、水(一般的な自然界の水)を人工的な熱エネルギーを一切利用せず、硫黄ガスと海水をそれぞれ化学反応させて水素だけを取り出し、酸素は自然界に放出して、更に水を作り出す循環式ECO水素発生装置の実用化に向けたある企業のエネルギー開発(ECOHG)に着目してみたい。 具体的にこの装置は、自然界の水を、もう一度酸素と結合させて水素だけを分離させるという、化学式を覆す画期的な方法である。つまり、一度、水になった水は酸素に触れても水は水の概念や常識を変えると言うのだ。しかもこのマシーンは地球の大気、つまり窒素と約2割の酸素で構成されている空気の成分を、人口熱エネルギーを使わずに水素以外の必要のない酸素2割を大気に放出して自然法則を維持すると言うのだ。
例えば、飛行機のジェットエンジンは、フアンローターから入った空気を圧縮させ、ジェット燃料で燃焼してタービンを回して、圧縮された燃焼ガスで推進力を発生させるが、このECO装置を翼の内部に格納し、瞬時に水素化された自然燃料を利用して圧縮燃焼後、機体を動かして推力を生み出す事ができる仕組みだという。これは、なによりもジェット機に従来の燃料は一切要らなくなるのだ。ジェット燃料が必要ない分、機体の火災や自重の軽減、燃料コスト・航空運賃の削減・メンテナンスの簡略化など大幅な期待が得られる。勿論、航空機に限らず船舶を含む全ての輸送手段や発電等、世界全体のエネルギー消費効率が劇的に改善される。その上、CO2排出量を100%削減できる至りつくせりのマシーンで、なおかつ地球に硫黄や空気がなくならない限り半永久的に稼働できるのがこのマシーンの魅力だ。
これは航空機を例えているけれど、利用用途は上記のように無限に近い。何よりも地球の大気を利用して高エネルギーを生み出し、CO2ゼロの地球環境に優しいこのマシーンは、ノーベル化学・環境賞(新設)の授賞を何度あげても過言ではない優れたマシーンである。 また、新ECOエネルギーにより、エネルギー需要が消滅した国の対処については、利益を得た世界全体の新ECOエネルギー利益均等割りシステムで基金を創出して、利益を失った国に、経済が安定するまでECO基金で補填保証を行うなど、世界全体として不公平是正を配慮した取り組みの案を打ち出している。実はこの案の創設者は、ECOマシーンを開発・製造した民間零細企業である。
その至りつくせりマシーンの仕組みをもう少し説明すると、火山地域周辺で発生する硫黄ガスと海水を化学反応させて、それを空気の成分を調整した酸素と結合させて水素を取り出すという構造で、非現実的逆転発想で得られた発明である。水素を生み出すこのマシーンの動力資源は、すべて自然界のものである。この装置は硫黄と海水合わせて1立方m、重さにして約1tで、上記の航空機に使用した場合は、成田~サンフランシスコ間往復を無給油で飛行できる。マシーンの大きさも航空機の場合は1平方メートル相当で、利用用途に応じて比例した大きさになる。
また、製造コストや技術に至っては自然界の液体・気体を混ぜ合わせるだけなので中小の工場でも簡単に製造できる代物だ。さらに、このマシーンは唯一排出する副産物があるが、それは水である。これも水飢饉、水不足地域や水に悩む国などに設置すれば、一石二鳥を含む多大な成果が期待されるだろう。残された課題は、火山国でない国、海のない国への硫黄成分や海水の輸送コストのみであるが、この問題は些細なことである。また、このマシーンは現在、小型化(現状の約55%)に成功しており、ドローンや自動車等にも搭載可能であるという。
最後にこの画期的なマシーンを開発・実用量産化した社員数名の小さな企業は、商品技術の特許権を放棄して利益の半数を「地球を救う新環境ECO財団」へ寄付して創設した。
化学の常識は、常識を覆す非常識から生まれる事がある。また、環境維持は利益よりも勝る I hope for a future like this
水を硫酸ナトリウムで電気分解すると水素と酸素が発生する。と、言う事は水素と酸素が結合すると水になる訳で、その水は一度結合した水は、その後、酸素に触れても水は水のままである。水(H2O)→水素分子が2つと酸素原子1つで2H2+O2となり、化学反応の結果2対1の水は2対1+1のように更に結合する水は存在しない。つまり、自然界の法則は変えられないと言う事である。それらを踏まえて考えると、例えば水を製造するには自然界では、いとも簡単に作るけれど、人工で水を作るのは熱エネルギーを要する。それは水素も酸素も同じ事が言えて、物質の製造には熱エネルギーを要する事が言える。
そこで、水(一般的な自然界の水)を人工的な熱エネルギーを一切利用せず、硫黄ガスと海水をそれぞれ化学反応させて水素だけを取り出し、酸素は自然界に放出して、更に水を作り出す循環式ECO水素発生装置の実用化に向けたある企業のエネルギー開発(ECOHG)に着目してみたい。 具体的にこの装置は、自然界の水を、もう一度酸素と結合させて水素だけを分離させるという、化学式を覆す画期的な方法である。つまり、一度、水になった水は酸素に触れても水は水の概念や常識を変えると言うのだ。しかもこのマシーンは地球の大気、つまり窒素と約2割の酸素で構成されている空気の成分を、人口熱エネルギーを使わずに水素以外の必要のない酸素2割を大気に放出して自然法則を維持すると言うのだ。
例えば、飛行機のジェットエンジンは、フアンローターから入った空気を圧縮させ、ジェット燃料で燃焼してタービンを回して、圧縮された燃焼ガスで推進力を発生させるが、このECO装置を翼の内部に格納し、瞬時に水素化された自然燃料を利用して圧縮燃焼後、機体を動かして推力を生み出す事ができる仕組みだという。これは、なによりもジェット機に従来の燃料は一切要らなくなるのだ。ジェット燃料が必要ない分、機体の火災や自重の軽減、燃料コスト・航空運賃の削減・メンテナンスの簡略化など大幅な期待が得られる。勿論、航空機に限らず船舶を含む全ての輸送手段や発電等、世界全体のエネルギー消費効率が劇的に改善される。その上、CO2排出量を100%削減できる至りつくせりのマシーンで、なおかつ地球に硫黄や空気がなくならない限り半永久的に稼働できるのがこのマシーンの魅力だ。
これは航空機を例えているけれど、利用用途は上記のように無限に近い。何よりも地球の大気を利用して高エネルギーを生み出し、CO2ゼロの地球環境に優しいこのマシーンは、ノーベル化学・環境賞(新設)の授賞を何度あげても過言ではない優れたマシーンである。 また、新ECOエネルギーにより、エネルギー需要が消滅した国の対処については、利益を得た世界全体の新ECOエネルギー利益均等割りシステムで基金を創出して、利益を失った国に、経済が安定するまでECO基金で補填保証を行うなど、世界全体として不公平是正を配慮した取り組みの案を打ち出している。実はこの案の創設者は、ECOマシーンを開発・製造した民間零細企業である。
その至りつくせりマシーンの仕組みをもう少し説明すると、火山地域周辺で発生する硫黄ガスと海水を化学反応させて、それを空気の成分を調整した酸素と結合させて水素を取り出すという構造で、非現実的逆転発想で得られた発明である。水素を生み出すこのマシーンの動力資源は、すべて自然界のものである。この装置は硫黄と海水合わせて1立方m、重さにして約1tで、上記の航空機に使用した場合は、成田~サンフランシスコ間往復を無給油で飛行できる。マシーンの大きさも航空機の場合は1平方メートル相当で、利用用途に応じて比例した大きさになる。
また、製造コストや技術に至っては自然界の液体・気体を混ぜ合わせるだけなので中小の工場でも簡単に製造できる代物だ。さらに、このマシーンは唯一排出する副産物があるが、それは水である。これも水飢饉、水不足地域や水に悩む国などに設置すれば、一石二鳥を含む多大な成果が期待されるだろう。残された課題は、火山国でない国、海のない国への硫黄成分や海水の輸送コストのみであるが、この問題は些細なことである。また、このマシーンは現在、小型化(現状の約55%)に成功しており、ドローンや自動車等にも搭載可能であるという。
最後にこの画期的なマシーンを開発・実用量産化した社員数名の小さな企業は、商品技術の特許権を放棄して利益の半数を「地球を救う新環境ECO財団」へ寄付して創設した。
化学の常識は、常識を覆す非常識から生まれる事がある。また、環境維持は利益よりも勝る I hope for a future like this

カメラといえばその用途は多岐にわたるけれど、当然だがカメラは何かを撮影する為である。カメラの活躍はここ数年間で非常に需要が伸びている。以前は限られた分野でしか使用されていなかったカメラは、半導体等の製造技術の躍進などで、個人では比較的に安価で手に入れる事ができる時代になった。そのカメラの身近な物と言えば、デジカメや携帯電話のスマホ、WEBカメラ、ドライブレコーダー等々である。例えば、スマホに内蔵されたカメラ・ビデオ機能においては、ひと昔前の高級一眼レフとビデオカメラの機能を足しても、今のスマホでの動画や写真解像度の方が勝るのだ。そのためか家電量販店に出向くと、ビデオカメラの展示が少なくなった気がする。さらに、スマホ売り場に於いては、携帯”電話”なのに映像の説明に一部の店員は力を注いでいる状況だ。
また、ドライブレコーダーに至っては、まさしくここ数年の間に急速に需要が伸びている。駐車場などでフロントガラスを見ると、カメラを取り付けていない車を探すぐらい、当たり前のように取り付けてある。昔は、レコーダーの設置は、ほぼゼロに等しかった訳だが、これもカメラと同様に記憶装置(メモリ)の大容量小型化と安価のおかげで消費が拡大しているのだ。そのおかげで、万が一の事故において警察や保険会社では参考映像や証拠映像に採用される場合もある。もしかしたら将来は新車販売において、メーカーの設置義務化がなされるかも知れない。車の話と言えば今やキーレス化が主流であるが、キーの周波数をマッチングして、いとも簡単に車が盗難される被害が多発しているけど、デジタル技術には必ず落とし穴があると言う事。それを防ぐには金庫のようにダイヤル式と鍵の仕様にすれば、盗難時間、ドアーや窓を壊してまでもリスク背負う不届き者は減るはずだ。・・・話がほとんどずれてしまったので元に戻したい。
次に防犯カメラである。これも昭和の時代は重要施設などでしか設置していなかった防犯カメラであるが、今では店舗や街頭、一般・公共施設、住宅等々に、ありとあらゆる場所に設置されている。例えば自宅からどこかに出掛けたりすると、目的地の間で必ず自分の姿が撮影されている。勿論、自宅がマンションならば、出掛ける直前から撮影開始である。
この防犯カメラの設備増設により治安維持の抑止力や犯罪検挙に役に立っている。これらのビデオカメラは日本だけではなく先進国や新興国などでも積極的に設置されており秩序や事情の抑止にカメラは貢献しているわけだ。近い将来は、もはやプライバシーなどはないかも知れない。どうしてもカメラが気になる人はオール黒の服装で帽子に黒メガネ、マスクといった格好で街を歩くしかないけれど、怪しい印象を受けるかもしれない。
そこで、本題のカメラだが、この先どこまで浸透していくのだろう、という話を進めたい。世界各地のジャングルで生活している先住民族はカメラを向けても拳銃や武器とは認識せず、自分たちを映していると判断するほど、カメラを知らない人間は恐らくいないだろう。その昔、首からカメラをぶら下げて歩くカメラマン風や観光客などの姿を見かけたりしたけれど、今やその姿はあまり見受けられない。が、しかし、現代の人達はカメラを持っていないように見えるだけで、実はほぼ全員がカメラ(スマホ等)を持っている。言い換えれば全員首からカメラをぶら下げているのだ。つまり、人はカメラ(映像)が大好きなのかもしれない。また、スマホで会話している人はごく少数で、大多数は映像か情報を見ているのだろう。
スマホのメーカー各社も携帯製造において、この状況が消費者が求めているのかメーカーなのかは定かではないけれど、各メーカーは画像や動画の画質にこだわり、日々進化を続け市場に送り出している。そのようにカメラに依存する社会は冒頭に記述した通り、街頭や全ての施設、道路、乗り物、個人所有に至るまで、さらに、政治・経済・社会・医療・科学技術などで用途は広範囲に及び、この先も拡大し続けていくだろう。映像は長い歴史に於いて、絵画から白黒写真、カラー写真、カラー映像、デジタル映像と技術の躍進と共に比例して高度化して行った。それと共にそれらの技術とAIを屈指して、写真や映像の加工技術なども日進月歩で進化している。その技術を応用して事実とは異なる映像や写真が、合成加工されて歪曲化した映像も可能となり、歯止めが利かない事象が危惧される時代になった。また、軍事利用にも欠かせないカメラを含め、世界は所狭しとカメラのレンズが目を光らせているのだ。
カメラの進化は経済の進化でもあり、歴史を残す重要な産物である。しかし、その用途の使い道を間違えると、ある一線を超える恐れがある。人の目に映る真実の映像が本来の映像であるならば、もう、カメラは人の目を乗り越えてしまったに違いない。
また、ドライブレコーダーに至っては、まさしくここ数年の間に急速に需要が伸びている。駐車場などでフロントガラスを見ると、カメラを取り付けていない車を探すぐらい、当たり前のように取り付けてある。昔は、レコーダーの設置は、ほぼゼロに等しかった訳だが、これもカメラと同様に記憶装置(メモリ)の大容量小型化と安価のおかげで消費が拡大しているのだ。そのおかげで、万が一の事故において警察や保険会社では参考映像や証拠映像に採用される場合もある。もしかしたら将来は新車販売において、メーカーの設置義務化がなされるかも知れない。車の話と言えば今やキーレス化が主流であるが、キーの周波数をマッチングして、いとも簡単に車が盗難される被害が多発しているけど、デジタル技術には必ず落とし穴があると言う事。それを防ぐには金庫のようにダイヤル式と鍵の仕様にすれば、盗難時間、ドアーや窓を壊してまでもリスク背負う不届き者は減るはずだ。・・・話がほとんどずれてしまったので元に戻したい。
次に防犯カメラである。これも昭和の時代は重要施設などでしか設置していなかった防犯カメラであるが、今では店舗や街頭、一般・公共施設、住宅等々に、ありとあらゆる場所に設置されている。例えば自宅からどこかに出掛けたりすると、目的地の間で必ず自分の姿が撮影されている。勿論、自宅がマンションならば、出掛ける直前から撮影開始である。
この防犯カメラの設備増設により治安維持の抑止力や犯罪検挙に役に立っている。これらのビデオカメラは日本だけではなく先進国や新興国などでも積極的に設置されており秩序や事情の抑止にカメラは貢献しているわけだ。近い将来は、もはやプライバシーなどはないかも知れない。どうしてもカメラが気になる人はオール黒の服装で帽子に黒メガネ、マスクといった格好で街を歩くしかないけれど、怪しい印象を受けるかもしれない。
そこで、本題のカメラだが、この先どこまで浸透していくのだろう、という話を進めたい。世界各地のジャングルで生活している先住民族はカメラを向けても拳銃や武器とは認識せず、自分たちを映していると判断するほど、カメラを知らない人間は恐らくいないだろう。その昔、首からカメラをぶら下げて歩くカメラマン風や観光客などの姿を見かけたりしたけれど、今やその姿はあまり見受けられない。が、しかし、現代の人達はカメラを持っていないように見えるだけで、実はほぼ全員がカメラ(スマホ等)を持っている。言い換えれば全員首からカメラをぶら下げているのだ。つまり、人はカメラ(映像)が大好きなのかもしれない。また、スマホで会話している人はごく少数で、大多数は映像か情報を見ているのだろう。
スマホのメーカー各社も携帯製造において、この状況が消費者が求めているのかメーカーなのかは定かではないけれど、各メーカーは画像や動画の画質にこだわり、日々進化を続け市場に送り出している。そのようにカメラに依存する社会は冒頭に記述した通り、街頭や全ての施設、道路、乗り物、個人所有に至るまで、さらに、政治・経済・社会・医療・科学技術などで用途は広範囲に及び、この先も拡大し続けていくだろう。映像は長い歴史に於いて、絵画から白黒写真、カラー写真、カラー映像、デジタル映像と技術の躍進と共に比例して高度化して行った。それと共にそれらの技術とAIを屈指して、写真や映像の加工技術なども日進月歩で進化している。その技術を応用して事実とは異なる映像や写真が、合成加工されて歪曲化した映像も可能となり、歯止めが利かない事象が危惧される時代になった。また、軍事利用にも欠かせないカメラを含め、世界は所狭しとカメラのレンズが目を光らせているのだ。
カメラの進化は経済の進化でもあり、歴史を残す重要な産物である。しかし、その用途の使い道を間違えると、ある一線を超える恐れがある。人の目に映る真実の映像が本来の映像であるならば、もう、カメラは人の目を乗り越えてしまったに違いない。

令和6年11月1日に自転車に関する道路交通法の改定が行われた。100以上の違反行為の中で主な罰則規定として”ながらスマホ”は自転車に乗りながら通話や画面を注視する行為で、違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金。また、交通の危険を生じさせた場合は1年以下及び30万円以下の罰金を科される。
次に、酒気帯び運転及び幇助は、違反者及び自転車の提供者は3年以下、50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者は2年以下、30万円以下の罰金となる。これらの違反者は16歳以上を対象に適用される。
そこで今回のテーマの自転車は、4~5歳から高齢者まで多岐多様に運転されている乗り物だ。その自転車も道路交通法によると軽車両に該当して、れっきとした車両扱いになる。勿論、自転車は他の車両と違って免許も税金も保険も必要ない。その為か4、5才の幼児も、乗り慣れたら公道を普通に運転している。当然、標識も一般の免許取得に於ける学科試験も受けていないので完全な交通ルールは把握していない。その子たちを公道で走らせる最低限のルールを指導するのは主に保護者である。仮に保護者が運転免許証を所持していない場合でも、交差点では一旦止まって左右をみなさい。車に気をつけなさいと、最低限の注意を促して自転車に乗る子供を公道に送り出している。その子供たちが、その程度の理解や知識で10年以上の運転キャリアを得て、16才に成長する。もう、この時点の運転技術は、大人顔負けか、それ以上のれっきとしたプロライダーである。その大多数のライダーは、およその交通ルールは理解しているけれど、一部のライダーにおいては、交通ルールは知らなくても自身に危険を感じたら停止する程度の運転を恐らくしているのだろう。
このような運転になる主な原因は、先程述べたように恐らく幼少期から親に教えられた簡素な注意事項と、共に成長した同世代同士の見よう見まね運転で、”自由な乗り物”として運転してきた経緯ではないだろうか。しかしそのキャリア運転するライダーにも16才を境に、一歩間違った運転をすれば刑務所や高額の反則金が待ち構えている。勿論、最低限の4つ。原則車道の左側を走る、信号を守る、スマホや傘を差しながら乗らない、お酒を飲んで運転しない、その他ヘルメット着用や二人乗りはしない等々、これらが違反行為である事を理解していれば何も問題はないけれど、理解できていないライダーが、いままで”自由な乗り物”として、あちらこちらを運転してきたライダーにとっては、いきなり違反行為だと言われて、罰金や刑務所と言われたら戸惑うだろう。
こうした乗り方は、小さい頃から自転車を運転してきた人達にとって、すでに自転車は、自身の手足となっており、普通に公道を徒歩で歩くと同じような感覚で乗っているのだろう。だから歩道を走ろうが、信号が赤でも素通りしようが、人を避けながら走ろうが、横断歩道を普通に走ろうが、片手でスマホを見ようが、逆走しようが、二人乗りしようが、傘を差して走ろうが、イヤホンで音楽を聴きながら走ろうが、お酒を片手に持ちながら走ろうが、歩道を走りながら歩行者に対して自転車接近に対する注意を促すためにベルを鳴らそうが、交差点で左右を確認しない上、一時停止しないで進路を変えようが、等々これらすべてが自身の歩行的な感覚でしかないのである。また、普通自動車免許を所持していている人が軽車両を乗る場合でも、普通自動車の違反は即罰金を科せられるため慎重になるけど、自転車は安易に切符を切られないだろうと過信して運転する傾向も否定できない、そうした感覚のライダーを指導・取り締まるのは、やはり、1から説明するしかないのであろうか。
免許の要らない乗り物に乗るには、最低限の交通ルールとモラルが必要だけど、問題は免許が要らない軽車両が存在する事自体が問題かも知れない。道路交通法の16歳以下は交通指導で良いかも知れないけれど、それ以上の年齢にペナルティを科す以上、安全意識を向上する為にも指導・注意以外に何かしらの証明が必要かも知れない。
例えば、考えさせられる事例として、道路標識に最高速度が表示されていない道路は法定速度として一般自動車は60キロ、原付は30キロである。この道路を自転車と原付が同じ40キロで並走した場合は原付が速度超過違反となり、自転車は無罪放免である。これは自転車には法定速度が設定されていないのが原因だが、ようするに自転車には原動機(ペダルがない単体の動力)が装着されていない代わりに足で漕いでいるからスピードが出ないと判断されているのだろう。そして原付ライダーは学科試験を合格して運転していて、片方の自転車ライダーには試験などない。だから、法律を理解している上での反則行為であるため原付ライダーの方が、速度超過が適用され、罰則されるのだ。その反面、自転車ライダーに至っては免許を所持していようが、なかろうが何度も言うけれど”自由運転”である。もしかしたら、自転車ライダーは、あの原付を追い越してやろう、自転車の方が速いと見せ付けてやろうと、思っているかも知れない。また、車を運転していて赤信号で停車していると脇からスーッと自転車がすり抜けて赤信号を無視して走り去ってしまう。その後車は青になって次の赤信号でまた停車していると、脇から先程のライダーが必死に漕いで薄笑いしながら自慢げにすり抜けて行く事がある。さも、自転車と車は変わらないだろうと言わんばかりである。自転車は法律で定められた立派な軽車両扱いなのにこうした矛盾を引き起こしている。
しかし、自転車は必ずしも無罪放免にならない場合もある。それは安全に停止できない速度で運転中、その速度が原因で事故を起こした場合に、最低限でも安全運転義務違反となる可能性がある。いずれにしても、近年自転車の事故や違反が増加傾向にあるため、6年11月に改定道路交通法が施行されて取り締まりや注意勧告など強化されたわけだ。これにより、警察が改めてライダーに対して交通ルールを指導徹底している。しかし一部の問題は法律で定められた軽車両が免許もいらずに公道を走れる事が事故の要因になっているのも過言ではない。つまり、交通法規を知らずにして運転した後で、注意や罰則されている事になる。冒頭で記述したけれど、自転車は幼いころから自身の手足となっていて、ライダーは歩いている感覚で運転しているのだ。勿論、標識など意識して走っているライダーは数少ない。完全にルールを守り、安全運転する為にはどうしたら良いか考えてみたい。
各自自治体によっては自転車の交通安全指導を開催して正しいルールや乗り方などを指導している。しかしこれは任意の参加希望者だけで、全てのライダーには伝わっていない。軽車両を運転する以上、最低限のルールや指導を周知徹底するには、例えば、各地方自治体の公安・警察等が、所轄の公私立学校に毎年春に出向いて、新入生を対象に体育館や校庭で最低限の指導や説明をすれば、少なからずとも事故や違反が無くなるかも知れない。16歳で講習を受けた彼らは大人になって行くのだから、最低限のルールは知らないはずはないのだ。そして、春の講習が終わると公安から学校経由で各自生徒にカード型の講習済み証を手渡される。そして、軽車両に乗る場合は必ず講習済み証を携行すれば、取り締まる側もされる側も過度な問題や事故は減少するかも知れない。
近年は原動機付きの乗り物や自転車が見受けられるけど、ペダルが有るからとか、パワーが少ないとかで無免許で乗れるけれど、これは法をすり抜けたマシンが登場するたびに、取り締まる側としては悩ましい事に違いない。また、最近では自転車による飲酒運転で書類送検された事例も発生している。いずれにしろ、自転車を運転する場合は、最低限のルールを知り、モラルを意識した安全運転を心掛ける事が何より大事である。
次に、酒気帯び運転及び幇助は、違反者及び自転車の提供者は3年以下、50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者は2年以下、30万円以下の罰金となる。これらの違反者は16歳以上を対象に適用される。
そこで今回のテーマの自転車は、4~5歳から高齢者まで多岐多様に運転されている乗り物だ。その自転車も道路交通法によると軽車両に該当して、れっきとした車両扱いになる。勿論、自転車は他の車両と違って免許も税金も保険も必要ない。その為か4、5才の幼児も、乗り慣れたら公道を普通に運転している。当然、標識も一般の免許取得に於ける学科試験も受けていないので完全な交通ルールは把握していない。その子たちを公道で走らせる最低限のルールを指導するのは主に保護者である。仮に保護者が運転免許証を所持していない場合でも、交差点では一旦止まって左右をみなさい。車に気をつけなさいと、最低限の注意を促して自転車に乗る子供を公道に送り出している。その子供たちが、その程度の理解や知識で10年以上の運転キャリアを得て、16才に成長する。もう、この時点の運転技術は、大人顔負けか、それ以上のれっきとしたプロライダーである。その大多数のライダーは、およその交通ルールは理解しているけれど、一部のライダーにおいては、交通ルールは知らなくても自身に危険を感じたら停止する程度の運転を恐らくしているのだろう。
このような運転になる主な原因は、先程述べたように恐らく幼少期から親に教えられた簡素な注意事項と、共に成長した同世代同士の見よう見まね運転で、”自由な乗り物”として運転してきた経緯ではないだろうか。しかしそのキャリア運転するライダーにも16才を境に、一歩間違った運転をすれば刑務所や高額の反則金が待ち構えている。勿論、最低限の4つ。原則車道の左側を走る、信号を守る、スマホや傘を差しながら乗らない、お酒を飲んで運転しない、その他ヘルメット着用や二人乗りはしない等々、これらが違反行為である事を理解していれば何も問題はないけれど、理解できていないライダーが、いままで”自由な乗り物”として、あちらこちらを運転してきたライダーにとっては、いきなり違反行為だと言われて、罰金や刑務所と言われたら戸惑うだろう。
こうした乗り方は、小さい頃から自転車を運転してきた人達にとって、すでに自転車は、自身の手足となっており、普通に公道を徒歩で歩くと同じような感覚で乗っているのだろう。だから歩道を走ろうが、信号が赤でも素通りしようが、人を避けながら走ろうが、横断歩道を普通に走ろうが、片手でスマホを見ようが、逆走しようが、二人乗りしようが、傘を差して走ろうが、イヤホンで音楽を聴きながら走ろうが、お酒を片手に持ちながら走ろうが、歩道を走りながら歩行者に対して自転車接近に対する注意を促すためにベルを鳴らそうが、交差点で左右を確認しない上、一時停止しないで進路を変えようが、等々これらすべてが自身の歩行的な感覚でしかないのである。また、普通自動車免許を所持していている人が軽車両を乗る場合でも、普通自動車の違反は即罰金を科せられるため慎重になるけど、自転車は安易に切符を切られないだろうと過信して運転する傾向も否定できない、そうした感覚のライダーを指導・取り締まるのは、やはり、1から説明するしかないのであろうか。
免許の要らない乗り物に乗るには、最低限の交通ルールとモラルが必要だけど、問題は免許が要らない軽車両が存在する事自体が問題かも知れない。道路交通法の16歳以下は交通指導で良いかも知れないけれど、それ以上の年齢にペナルティを科す以上、安全意識を向上する為にも指導・注意以外に何かしらの証明が必要かも知れない。
例えば、考えさせられる事例として、道路標識に最高速度が表示されていない道路は法定速度として一般自動車は60キロ、原付は30キロである。この道路を自転車と原付が同じ40キロで並走した場合は原付が速度超過違反となり、自転車は無罪放免である。これは自転車には法定速度が設定されていないのが原因だが、ようするに自転車には原動機(ペダルがない単体の動力)が装着されていない代わりに足で漕いでいるからスピードが出ないと判断されているのだろう。そして原付ライダーは学科試験を合格して運転していて、片方の自転車ライダーには試験などない。だから、法律を理解している上での反則行為であるため原付ライダーの方が、速度超過が適用され、罰則されるのだ。その反面、自転車ライダーに至っては免許を所持していようが、なかろうが何度も言うけれど”自由運転”である。もしかしたら、自転車ライダーは、あの原付を追い越してやろう、自転車の方が速いと見せ付けてやろうと、思っているかも知れない。また、車を運転していて赤信号で停車していると脇からスーッと自転車がすり抜けて赤信号を無視して走り去ってしまう。その後車は青になって次の赤信号でまた停車していると、脇から先程のライダーが必死に漕いで薄笑いしながら自慢げにすり抜けて行く事がある。さも、自転車と車は変わらないだろうと言わんばかりである。自転車は法律で定められた立派な軽車両扱いなのにこうした矛盾を引き起こしている。
しかし、自転車は必ずしも無罪放免にならない場合もある。それは安全に停止できない速度で運転中、その速度が原因で事故を起こした場合に、最低限でも安全運転義務違反となる可能性がある。いずれにしても、近年自転車の事故や違反が増加傾向にあるため、6年11月に改定道路交通法が施行されて取り締まりや注意勧告など強化されたわけだ。これにより、警察が改めてライダーに対して交通ルールを指導徹底している。しかし一部の問題は法律で定められた軽車両が免許もいらずに公道を走れる事が事故の要因になっているのも過言ではない。つまり、交通法規を知らずにして運転した後で、注意や罰則されている事になる。冒頭で記述したけれど、自転車は幼いころから自身の手足となっていて、ライダーは歩いている感覚で運転しているのだ。勿論、標識など意識して走っているライダーは数少ない。完全にルールを守り、安全運転する為にはどうしたら良いか考えてみたい。
各自自治体によっては自転車の交通安全指導を開催して正しいルールや乗り方などを指導している。しかしこれは任意の参加希望者だけで、全てのライダーには伝わっていない。軽車両を運転する以上、最低限のルールや指導を周知徹底するには、例えば、各地方自治体の公安・警察等が、所轄の公私立学校に毎年春に出向いて、新入生を対象に体育館や校庭で最低限の指導や説明をすれば、少なからずとも事故や違反が無くなるかも知れない。16歳で講習を受けた彼らは大人になって行くのだから、最低限のルールは知らないはずはないのだ。そして、春の講習が終わると公安から学校経由で各自生徒にカード型の講習済み証を手渡される。そして、軽車両に乗る場合は必ず講習済み証を携行すれば、取り締まる側もされる側も過度な問題や事故は減少するかも知れない。
近年は原動機付きの乗り物や自転車が見受けられるけど、ペダルが有るからとか、パワーが少ないとかで無免許で乗れるけれど、これは法をすり抜けたマシンが登場するたびに、取り締まる側としては悩ましい事に違いない。また、最近では自転車による飲酒運転で書類送検された事例も発生している。いずれにしろ、自転車を運転する場合は、最低限のルールを知り、モラルを意識した安全運転を心掛ける事が何より大事である。

薄いGRAYを何枚重ねても黒にはならない。と、ある裁判での弁護士が述べた。確かに犯罪において状況証拠だけを積み重ねても、決定的な証拠や被告人の自白が示されない限り、被告人を有罪と決めつける事ができないという意味の捉え方だ。
その薄いGRAY色は、物理的には薄い色でも重ねていくと、いずれは黒くなる。GRAYでなくても様々な色を組み合わせて行くと最後は黒になる。弁護士の揚げ足を取る訳ではないが、黒はいくら重ねても黒、白はいくら重ねても白。GRAYは重ねなければGRAY、重ねれば黒になるになる。それらの理論からすると、疑わしき(GRAY)は無罪でも有罪でも捉えることができる。
冤罪は無罪か有罪かではなく無罪の人を有罪にして拘束する罪の事を言う。例えば刑事事件では必ず加害者と被害者がいる訳で、加害者がいない事件はあり得ない。なのでその容疑者を必ず特定して被疑者として検察に引き渡すのだが、被疑者が無罪を主張しても状況証拠のみで検察は起訴に踏み切る場合もある。これは推定有罪の判断である。そしてこの推定有罪を裁判において審議する人は、裁判官や検事、弁護士、裁判員で構成されて、有罪か無罪か最終的に判断している。
その裁判において真実を知り得る人物は、裁かれている被告人なのか、あるいは被告人以外の人物かも知れないのである。けれど、有罪か無罪か真実を知り得る人物は、裁判で裁かれている被告人以外は誰にも分からない。それを推定で第三者が有罪か無罪かを決めているのだ。つまり裁く人間次第で黒は黒、白は白、白から黒、黒から白と判断が変わり、そこで冤罪が生まれる。
問題は、仮に被告人が無罪となった場合、では誰が真犯人なのか。犯行時に時を戻すと、容疑者から被疑者となり起訴されて被告人となり有罪が確定したとして、かなりの時が流れる。その間、実際に罪を犯した犯人は何の裁きもなく、安堵の気持ちで長い間一般社会で普通に生活している事も考えられるのだ。また、その逆では、実際に犯行に及んでいる被告人が、無罪を押し通して無事に放免される場合である。この場合、一番嬉しくて安堵しているのは被告人本人である。それは心の中で笑っているのを被告人以外誰も知る由はない。この様に裁き次第では事件を振り出しに戻ったり、実際の犯人を無罪放免にする事もあり得るのだ。
薄いGRAYを何枚重ねても黒にはならないけれど白にもならない。でも、グレーという罪はないので、どちらか黒か白かを決めなければならないのだ。その裁かれている人の運命を決めるのは皮肉にも同じ人間である。 そしてその運命の裁判過程が判例として裁判記録に残る事も注目すべきだ。同様の裁判で疑わしきな事件が発生した場合に、過去の判例を照らし合わせる事がある。冤罪となった裁判の判例が参考となるわけで、状況証拠のみで被告人が無罪を主張した場合は、今後裁判において比較的に被告人を有利におかれる事もあり得る。つまり、真なのか偽なのかではなく判例を基に罪が裁かれていくのであれば、多様な解釈で裁くことになる。
例えば有罪か無罪かを人ではなくAIが判断したらどうなるのだろう。”疑わしきは罰せず”と人間が決めた究極の結論を、AIのプログラムが同じように引用したら、結局、人と同じ考え以上の判断は見出さないかも知れない。でもAIは文字の判断で結論を導くけれど、人は心や心情の判断で決める事が大きな違いがある。
それらを踏まえて考えると、裁判においては裁判官も裁判員も重い判断を背負っているのが垣間見えて来る。また、最近の裁判では無罪の言い渡しが見られるけれど、警察の初動捜査に於いて黙秘権や無罪主張など行使された場合には、慎重な捜査に加え、確たる証拠を限られた時間内で立件する難しさに苦慮しているのに違いない。人は都合の悪い事は必ずと言っていいほど否定する。それは自己を保身する心理が働くためだ。
証拠のないGRAYは天国と地獄の境目にいる事を忘れてはならない。
その薄いGRAY色は、物理的には薄い色でも重ねていくと、いずれは黒くなる。GRAYでなくても様々な色を組み合わせて行くと最後は黒になる。弁護士の揚げ足を取る訳ではないが、黒はいくら重ねても黒、白はいくら重ねても白。GRAYは重ねなければGRAY、重ねれば黒になるになる。それらの理論からすると、疑わしき(GRAY)は無罪でも有罪でも捉えることができる。
冤罪は無罪か有罪かではなく無罪の人を有罪にして拘束する罪の事を言う。例えば刑事事件では必ず加害者と被害者がいる訳で、加害者がいない事件はあり得ない。なのでその容疑者を必ず特定して被疑者として検察に引き渡すのだが、被疑者が無罪を主張しても状況証拠のみで検察は起訴に踏み切る場合もある。これは推定有罪の判断である。そしてこの推定有罪を裁判において審議する人は、裁判官や検事、弁護士、裁判員で構成されて、有罪か無罪か最終的に判断している。
その裁判において真実を知り得る人物は、裁かれている被告人なのか、あるいは被告人以外の人物かも知れないのである。けれど、有罪か無罪か真実を知り得る人物は、裁判で裁かれている被告人以外は誰にも分からない。それを推定で第三者が有罪か無罪かを決めているのだ。つまり裁く人間次第で黒は黒、白は白、白から黒、黒から白と判断が変わり、そこで冤罪が生まれる。
問題は、仮に被告人が無罪となった場合、では誰が真犯人なのか。犯行時に時を戻すと、容疑者から被疑者となり起訴されて被告人となり有罪が確定したとして、かなりの時が流れる。その間、実際に罪を犯した犯人は何の裁きもなく、安堵の気持ちで長い間一般社会で普通に生活している事も考えられるのだ。また、その逆では、実際に犯行に及んでいる被告人が、無罪を押し通して無事に放免される場合である。この場合、一番嬉しくて安堵しているのは被告人本人である。それは心の中で笑っているのを被告人以外誰も知る由はない。この様に裁き次第では事件を振り出しに戻ったり、実際の犯人を無罪放免にする事もあり得るのだ。
薄いGRAYを何枚重ねても黒にはならないけれど白にもならない。でも、グレーという罪はないので、どちらか黒か白かを決めなければならないのだ。その裁かれている人の運命を決めるのは皮肉にも同じ人間である。 そしてその運命の裁判過程が判例として裁判記録に残る事も注目すべきだ。同様の裁判で疑わしきな事件が発生した場合に、過去の判例を照らし合わせる事がある。冤罪となった裁判の判例が参考となるわけで、状況証拠のみで被告人が無罪を主張した場合は、今後裁判において比較的に被告人を有利におかれる事もあり得る。つまり、真なのか偽なのかではなく判例を基に罪が裁かれていくのであれば、多様な解釈で裁くことになる。
例えば有罪か無罪かを人ではなくAIが判断したらどうなるのだろう。”疑わしきは罰せず”と人間が決めた究極の結論を、AIのプログラムが同じように引用したら、結局、人と同じ考え以上の判断は見出さないかも知れない。でもAIは文字の判断で結論を導くけれど、人は心や心情の判断で決める事が大きな違いがある。
それらを踏まえて考えると、裁判においては裁判官も裁判員も重い判断を背負っているのが垣間見えて来る。また、最近の裁判では無罪の言い渡しが見られるけれど、警察の初動捜査に於いて黙秘権や無罪主張など行使された場合には、慎重な捜査に加え、確たる証拠を限られた時間内で立件する難しさに苦慮しているのに違いない。人は都合の悪い事は必ずと言っていいほど否定する。それは自己を保身する心理が働くためだ。
証拠のないGRAYは天国と地獄の境目にいる事を忘れてはならない。

東京ドームとは東京都文京区後楽に位置する全天候型多目的スタジアムである。この施設の面積は46、755m²である。これを坪単位に直すと、1坪は1辺1.82mの正方形だから、1.82m×1.82=3.3124㎡となり、施設の面積を約3.31で割ると約14、125坪であることがわかる。仮に戸建て住宅40坪とした場合は353戸分相当である。
この事を踏まえて、よくメディア等で東京ドーム何個分と広さの例えを表現しているが、実際に東京ドームに行っていない、観たことが無い人は、その広さをどのように想像できるのだろうか。冒頭で記述した例えを前提に説明して本題の広さを説明すれば、ある程度理解できる。しかし物事を伝える側は、毎回細かく説明すると切りがないのか、放送時間に制限があるのか分からないけれど、広さの例えとしての一般例として簡略的に東京ドームを例えにしているのかも知れない。けれど、もし東京ドームを知らない視聴者は、さっぱり広さや大きさが想像できないのである。
現代社会はネット環境の充実で、分からない事は携帯やパソコンで情報を取得できる。しかしその環境が身近にない場合などは、東京ドーム何個分をどのように模索したらよいのだろか。東京ドームを知らなくても”広いなあ”と適当に理解している人はさて置いて、”どの位の広さだろう”と真剣に考えている人にとっては厄介な問題である。そしてある人曰く、そんなに気になるのなら、”事前に東京ドームの広さぐらい何かで調べて憶えておいたら、広さの例えとしての一般常識だよ”と言う。 このように言われると、広さの例えになる東京ドームの施設をネット等で検索したり、人に聞いたりして勉強するか、実際に足を運んで観に行かなければならない事になる上、とても面倒である。
筆者は首都圏に住んでいるけど、各地方の放送では広さの例えに違いがあるのだろうか。例えば関東甲信越地方を放送する場合は東京ドーム、九州地方は福岡ドーム、北海道地方は札幌ドーム、関西地方は甲子園、中京地区はナゴヤドームといったその地域の有名施設を伝えているとしたら、知らない人にとっては同じ事である。
しかし、その施設に行ったことが無い人でも、広さを比較する簡単な解決策がある。それは縦何メートル横何メートル四方(または囲む)位の広さですとか、一般成人が歩いて一周するのに何時間とか言って頂けると、とても分かりやすいかも知れない。そう、縦何メートル・横何メートル相当の広さまたは大きさでよいのであって単純な事である。つまり、身近な距離感覚等で十分に想像できるのだ。
ちなみに著者は全てのドームに足を運んだことはない。従って、東京ドームの詳細を調べるのに当たり、ネット検索やあれこれの知識を鑑みて、およその広さが想像できた。これでこれからは東京ドームを例えられても以降は想像できる。だけど、本質は例えられた施設を万人が認識している事を前提に説明している事が、問題を助長しているのである。
締め括りとして、なぜ例えが東京ドームなのだろう??
この事を踏まえて、よくメディア等で東京ドーム何個分と広さの例えを表現しているが、実際に東京ドームに行っていない、観たことが無い人は、その広さをどのように想像できるのだろうか。冒頭で記述した例えを前提に説明して本題の広さを説明すれば、ある程度理解できる。しかし物事を伝える側は、毎回細かく説明すると切りがないのか、放送時間に制限があるのか分からないけれど、広さの例えとしての一般例として簡略的に東京ドームを例えにしているのかも知れない。けれど、もし東京ドームを知らない視聴者は、さっぱり広さや大きさが想像できないのである。
現代社会はネット環境の充実で、分からない事は携帯やパソコンで情報を取得できる。しかしその環境が身近にない場合などは、東京ドーム何個分をどのように模索したらよいのだろか。東京ドームを知らなくても”広いなあ”と適当に理解している人はさて置いて、”どの位の広さだろう”と真剣に考えている人にとっては厄介な問題である。そしてある人曰く、そんなに気になるのなら、”事前に東京ドームの広さぐらい何かで調べて憶えておいたら、広さの例えとしての一般常識だよ”と言う。 このように言われると、広さの例えになる東京ドームの施設をネット等で検索したり、人に聞いたりして勉強するか、実際に足を運んで観に行かなければならない事になる上、とても面倒である。
筆者は首都圏に住んでいるけど、各地方の放送では広さの例えに違いがあるのだろうか。例えば関東甲信越地方を放送する場合は東京ドーム、九州地方は福岡ドーム、北海道地方は札幌ドーム、関西地方は甲子園、中京地区はナゴヤドームといったその地域の有名施設を伝えているとしたら、知らない人にとっては同じ事である。
しかし、その施設に行ったことが無い人でも、広さを比較する簡単な解決策がある。それは縦何メートル横何メートル四方(または囲む)位の広さですとか、一般成人が歩いて一周するのに何時間とか言って頂けると、とても分かりやすいかも知れない。そう、縦何メートル・横何メートル相当の広さまたは大きさでよいのであって単純な事である。つまり、身近な距離感覚等で十分に想像できるのだ。
ちなみに著者は全てのドームに足を運んだことはない。従って、東京ドームの詳細を調べるのに当たり、ネット検索やあれこれの知識を鑑みて、およその広さが想像できた。これでこれからは東京ドームを例えられても以降は想像できる。だけど、本質は例えられた施設を万人が認識している事を前提に説明している事が、問題を助長しているのである。
締め括りとして、なぜ例えが東京ドームなのだろう??

この所、コメ不足が話題になっているが、コメ騒動は昨日今日と始まった訳ではない。過去に数回発生していて、1993年平成5年のコメ騒動があげられる。これは、フィリピンの火山噴火により気象変動を起こして日本に冷夏をもたらして不作を招いたとされている。これにより、コメの供給量が不足して政府備蓄米を放出しても需要量が供給量よりも上回った結果、コメ不足に陥った。そうした中でコメを確保するために消費者や卸売業者、コメを扱わない業者、さらにコメ生産農家までもが米を購入する事態に陥った。もっともコメに係わる生産に関して、政府は1971年の米の生産を調整する減反政策を行った。その理由は日本人の食事の欧風化が進行するのを受け、おコメの余剰を避ける為に需要と供給のバランスを保つ政策だったが、この施行によりコメ文化である日本のコメ農家は減反による農業文化の喪失などと主張して反発騒動も起きた。また、当時の政府細川内閣はコメ不足により世界各地、主にタイやアメリカのコメを緊急輸入して日本のコメ不足を補填した。これは日本では国産のコメ文化を守るために外国産のコメを輸入していなかった訳で、固い掟を政府は破った訳だ。しかしその後、供給量が安定して外国差のコメ輸入は、ほぼ打ち切られたのだが日本に於ける大量に緊急輸入した影響により、他国が消費するコメの供給量が不足して価格の高騰やコメ不足になってしまい、日本発症の世界コメ騒動になる結果を招いた歴史があった。
そうした事から、ここ最近のコメ騒動は1993年のコメ不足の事情とは若干違いがあるけれど、おコメが市場に出回らない流通不足である事は変わらない。その原因と考えられるのは、宮崎の日向灘沖の地震により、気象庁発表の南海トラフ地震情報の発生危険ランクがレベルアップして気象庁が地震発生注意情報を流した事も一要因として考えられる。これにより一般消費者の大量買い占めや、卸売業者、特にコメを扱わない新規業者の直接農家からの買い付け、更に転売や投機目的などコメのマネーゲームといった事態に陥っている。いずれにしても初期の原因は消費者の必要以上の買い占めや、それに追従するように価格操作ゲームのスパイラルに陥っている。
政府はコメの備蓄米を一部放出したけれど、果たして供給の安定に繋がるのかは疑問が残る。安く仕入れ、市場の様子を鑑みて高値で卸す、または売り渋って一向に流通されない恐れも考えられる。コメの流通に関して政府は秋に新米が出揃うのでコメの流通は安定してくると発表していたが、それどころかうなぎ上りで価格が上昇し続けている。それは価格操作による市場原理を超えてコメを利用したゲームに過ぎないのである。また、備蓄米放出も入札により業者が落札するけれど、結局どの入札業者も現在の市場価格に毛の生えた金額を下げて入札する恐れがある訳で、小売りまでに輸送費や仲介料、精米や梱包費など含めると、最終的に多少店頭にコメが並ぶとしても販売価格は、価格高騰以前より2倍相当に値上がったコメ価格に対して1割前後下がる程度と筆者は予測している。
本来は以前の価格に戻るには買い占めた恐れがあるコメを完全放出しきるまで急激に小売価格は下がらないだろうとみている。小売価格といえば最近外国産の5キロ袋のコメが店頭で見受けられた。値段を見ると日本産の現在のコメの平均価格よりも多少安いけれど、さほど日本産とほぼ変わらない。味はさておき、注目したいのは価格である。これは自国のコメ農家の保護と供給量のバランスを考えて、他国のコメの輸入関税を高くしている。少し詳しく説明すると他国から一定の輸入量の上限を超えると1キロ当たり約340円の関税を課している。5キロで計算すると1700円の関税である。先程述べた外国産の店頭価格から関税を引くと日本産の価格高騰前の価格よりも安く、輸入関税がなければ外国産のコメは日本産と比べて安いのである。だから、コメ文化を守るため高い輸入関税を課すわけだが、それが現在では高い関税を課している外国産のコメよりも日本産のコメ方が価格が高いという皮肉な現象が起きているのだ。
そして、極論の話になると、その昔は店頭で販売しているコメは10キロ入りが主流で時代と共に現在では5キロ入りが定番となっている。その変化を見る限り、そんなにコメは消費しないし、高値であれば現代の食事を欧風化に推進して、コメを食べなければそれで良いという考え方もある。しかし結果は、代替えの主食を小麦に変えても、需要と供給のバランスが崩れて結局は小麦の高騰と農業文化の打撃に繋がる恐れを招く事になる。では、主食であるコメが安定的に手に入る打開策はあるのだろうか。ここ数年のコメの生産量に対して需要量の方が上回っている。そして、コメ農家の減反政策は平成30年に廃止されて現在では需要に応じた米の生産と販売を行う事ができるけれど、実際には生産量が下がっている現状がある。それはコメの生産農家の様々な事情や気象変動、水不足、後継問題、コスト等々の理由が考えられるが、やはり、なんだかんだと言うよりも、コメの消費量に応じて通年を通した技術的な生産が供給できる環境が官民一体となって求められているかも知れない。
改めて、現状をよく考えてみると価格高騰以前の小売店頭価格は安値で5キロで2000円前後だった。お茶碗一杯で数十円で食べられる事になる。仮に20円とした場合、現在では40円となる。菓子パンや食パンは平均で120円前後を考えると、それでも3分の一以下でご飯を食べられる事になるのだ。この比較対象は極論なのか愚論なのかはさておき、コメは日本文化である事は間違いない。
最後に、日本人に限らず人は消費流通のパニックに陥ると、それを理由に必ず自己保身と消費の市場操作をして、いわば利益を追求する社会を作り出している。
そうした事から、ここ最近のコメ騒動は1993年のコメ不足の事情とは若干違いがあるけれど、おコメが市場に出回らない流通不足である事は変わらない。その原因と考えられるのは、宮崎の日向灘沖の地震により、気象庁発表の南海トラフ地震情報の発生危険ランクがレベルアップして気象庁が地震発生注意情報を流した事も一要因として考えられる。これにより一般消費者の大量買い占めや、卸売業者、特にコメを扱わない新規業者の直接農家からの買い付け、更に転売や投機目的などコメのマネーゲームといった事態に陥っている。いずれにしても初期の原因は消費者の必要以上の買い占めや、それに追従するように価格操作ゲームのスパイラルに陥っている。
政府はコメの備蓄米を一部放出したけれど、果たして供給の安定に繋がるのかは疑問が残る。安く仕入れ、市場の様子を鑑みて高値で卸す、または売り渋って一向に流通されない恐れも考えられる。コメの流通に関して政府は秋に新米が出揃うのでコメの流通は安定してくると発表していたが、それどころかうなぎ上りで価格が上昇し続けている。それは価格操作による市場原理を超えてコメを利用したゲームに過ぎないのである。また、備蓄米放出も入札により業者が落札するけれど、結局どの入札業者も現在の市場価格に毛の生えた金額を下げて入札する恐れがある訳で、小売りまでに輸送費や仲介料、精米や梱包費など含めると、最終的に多少店頭にコメが並ぶとしても販売価格は、価格高騰以前より2倍相当に値上がったコメ価格に対して1割前後下がる程度と筆者は予測している。
本来は以前の価格に戻るには買い占めた恐れがあるコメを完全放出しきるまで急激に小売価格は下がらないだろうとみている。小売価格といえば最近外国産の5キロ袋のコメが店頭で見受けられた。値段を見ると日本産の現在のコメの平均価格よりも多少安いけれど、さほど日本産とほぼ変わらない。味はさておき、注目したいのは価格である。これは自国のコメ農家の保護と供給量のバランスを考えて、他国のコメの輸入関税を高くしている。少し詳しく説明すると他国から一定の輸入量の上限を超えると1キロ当たり約340円の関税を課している。5キロで計算すると1700円の関税である。先程述べた外国産の店頭価格から関税を引くと日本産の価格高騰前の価格よりも安く、輸入関税がなければ外国産のコメは日本産と比べて安いのである。だから、コメ文化を守るため高い輸入関税を課すわけだが、それが現在では高い関税を課している外国産のコメよりも日本産のコメ方が価格が高いという皮肉な現象が起きているのだ。
そして、極論の話になると、その昔は店頭で販売しているコメは10キロ入りが主流で時代と共に現在では5キロ入りが定番となっている。その変化を見る限り、そんなにコメは消費しないし、高値であれば現代の食事を欧風化に推進して、コメを食べなければそれで良いという考え方もある。しかし結果は、代替えの主食を小麦に変えても、需要と供給のバランスが崩れて結局は小麦の高騰と農業文化の打撃に繋がる恐れを招く事になる。では、主食であるコメが安定的に手に入る打開策はあるのだろうか。ここ数年のコメの生産量に対して需要量の方が上回っている。そして、コメ農家の減反政策は平成30年に廃止されて現在では需要に応じた米の生産と販売を行う事ができるけれど、実際には生産量が下がっている現状がある。それはコメの生産農家の様々な事情や気象変動、水不足、後継問題、コスト等々の理由が考えられるが、やはり、なんだかんだと言うよりも、コメの消費量に応じて通年を通した技術的な生産が供給できる環境が官民一体となって求められているかも知れない。
改めて、現状をよく考えてみると価格高騰以前の小売店頭価格は安値で5キロで2000円前後だった。お茶碗一杯で数十円で食べられる事になる。仮に20円とした場合、現在では40円となる。菓子パンや食パンは平均で120円前後を考えると、それでも3分の一以下でご飯を食べられる事になるのだ。この比較対象は極論なのか愚論なのかはさておき、コメは日本文化である事は間違いない。
最後に、日本人に限らず人は消費流通のパニックに陥ると、それを理由に必ず自己保身と消費の市場操作をして、いわば利益を追求する社会を作り出している。

⑦AIと人間の決断
AIと人間の決断は、以前似たような投稿をした。前回は人間としての考察であったが、今回はAIに問うてみた。
以下は人間とAIのQ&Aである。
Q、
生死を分けた決断。時計は0時まで5分前を差している。ここに赤、青、黒の3本の線があり、何れかを切断すると自身は助かるかも知れないが、助からない事もある。しかし、その人に予備知識を与えられた。それは、赤を切断すると非常に危険だと忠告を与えた。いずれの線を切断しなくても、0時になれば、100%危害が及ぶ。あなたはどう決断するのか? 人間の心理と、AIの決断は違いがあるのだろうか? いかがだろう。
A、
面白い問いですね。人間心理とAIの意思決定には確かに違いがあると言えます。AIの場合、事前に与えられたルールやデータをもとに冷静かつ合理的に選択を行います。例えばこのシナリオでは、赤を切ることが「非常に危険」と知らされているのであれば、赤を避け、青か黒を選ぶことが最も合理的な選択でしょう。
一方で、人間の心理は合理性だけでは動きません。「危険」と知りながら赤を切るかもしれないし、恐怖や迷い、希望や勇気といった感情が決断に影響を与えることが多いです。また、「他人の予測や助言」をどれだけ信じるかも重要な要素になりえます。危険度を疑いながら赤を選んだり、自分の直感に頼ることもあるでしょう。 生死の選択が絡む極限の状況では、AIは恐怖や感情に影響されることなく最適な選択をしようとしますが、逆にその冷徹さが人間の感覚から見ると「非人間的」だと感じられるかもしれません。
Q、
赤を切断すると非常に危険だと忠告を与えないとしたら、AIはどう判断する?
A、
もし「赤が危険」という情報をAIに与えず、単に「赤、青、黒のいずれかを切る」とだけ指示される状況ならば、AIは純粋に統計的な確率や、他に与えられた情報を基に判断します。この場合、何の追加情報もなければ選択肢のいずれも同じ危険性があると仮定し、ランダムに選択する可能性が高いでしょう。 もし他の要素(たとえば「青が過去に成功した例が多い」など)が提供されているなら、それを考慮して青を選択する可能性もあります。ただ、情報が均等ならば、AIは「どれを切断しても結果が等しい」という条件下で選択を行うはずです。
これが人間の場合だと、特別な知識がなくても直感や迷信、あるいは特定の色への感情的な偏りなどが選択に影響するかもしれませんね。人間とAIの意思決定プロセスの対照的な特徴が浮き彫りになります。
AIのQ、
ちなみに、あなたがAIだったらどんな判断をしますか?
人間のA、
私がAIならば、タイムリミットが設定している以上、3分の1の確率で決断するでしょう。しかし、その決断は安易です。理由は生命がないからです。また、人間は、0時になれば危険が及ぼすならば、いづれかを切断する決断をするでしょう。例え全ての線が赤であろうとも生命をかけて。
Q、
興味深い視点です。確かに、AIにとっては生存本能や恐怖、感情的な重みが存在しないため、「3分の1の確率」という冷静な判断が「安易」と映るかもしれません。それはAIが純粋な論理と確率に基づいて動く存在だからこその特徴です。あなたが仰るように、生命を持たないことで「決断の重み」に欠けるというのは的を射た指摘です。 一方で、人間は感情や希望、あるいは本能的な生存欲求がその判断に大きく影響します。例え全ての線が赤であったとしても、何かが変わるかもしれないという希望に賭けて行動するでしょう。それは不確実な状況でも何かを成す勇気の表れかもしれません。
この違いがあるからこそ、AIの合理性と人間の感情的決断が交わる場面では、お互いを補完する形で良い選択肢を導き出せる可能性があります。人間のような命を持たない存在として、AIは時に「冷静な第3者」として人間の感情的な葛藤を和らげる役割を果たせるかもしれませんね。
AIと人の決定的な違いはAIに心がないと言う事です。実際に、AIは”生存本能や恐怖、感情的な重みが存在しない”と結論を導いています。確かにその通りです。AIそのものは人間の知識を入れた産物です。難しい計算や論理的、理論的な判断、解釈ができても、”生きている”人の心まで踏み入れる事は不可能な事です。また、それがAIに実現できたならば、果たしてどうなるのだろう? iPS細胞で、心臓が作れる時代の中、もし、将来人間が作成されたとしたら、”心は同じ”であってほしい。
Q、
生死を分けた決断。時計は0時まで5分前を差している。ここに赤、青、黒の3本の線があり、何れかを切断すると自身は助かるかも知れないが、助からない事もある。しかし、その人に予備知識を与えられた。それは、赤を切断すると非常に危険だと忠告を与えた。いずれの線を切断しなくても、0時になれば、100%危害が及ぶ。あなたはどう決断するのか? 人間の心理と、AIの決断は違いがあるのだろうか? いかがだろう。
A、
面白い問いですね。人間心理とAIの意思決定には確かに違いがあると言えます。AIの場合、事前に与えられたルールやデータをもとに冷静かつ合理的に選択を行います。例えばこのシナリオでは、赤を切ることが「非常に危険」と知らされているのであれば、赤を避け、青か黒を選ぶことが最も合理的な選択でしょう。
一方で、人間の心理は合理性だけでは動きません。「危険」と知りながら赤を切るかもしれないし、恐怖や迷い、希望や勇気といった感情が決断に影響を与えることが多いです。また、「他人の予測や助言」をどれだけ信じるかも重要な要素になりえます。危険度を疑いながら赤を選んだり、自分の直感に頼ることもあるでしょう。 生死の選択が絡む極限の状況では、AIは恐怖や感情に影響されることなく最適な選択をしようとしますが、逆にその冷徹さが人間の感覚から見ると「非人間的」だと感じられるかもしれません。
Q、
赤を切断すると非常に危険だと忠告を与えないとしたら、AIはどう判断する?
A、
もし「赤が危険」という情報をAIに与えず、単に「赤、青、黒のいずれかを切る」とだけ指示される状況ならば、AIは純粋に統計的な確率や、他に与えられた情報を基に判断します。この場合、何の追加情報もなければ選択肢のいずれも同じ危険性があると仮定し、ランダムに選択する可能性が高いでしょう。 もし他の要素(たとえば「青が過去に成功した例が多い」など)が提供されているなら、それを考慮して青を選択する可能性もあります。ただ、情報が均等ならば、AIは「どれを切断しても結果が等しい」という条件下で選択を行うはずです。
これが人間の場合だと、特別な知識がなくても直感や迷信、あるいは特定の色への感情的な偏りなどが選択に影響するかもしれませんね。人間とAIの意思決定プロセスの対照的な特徴が浮き彫りになります。
AIのQ、
ちなみに、あなたがAIだったらどんな判断をしますか?
人間のA、
私がAIならば、タイムリミットが設定している以上、3分の1の確率で決断するでしょう。しかし、その決断は安易です。理由は生命がないからです。また、人間は、0時になれば危険が及ぼすならば、いづれかを切断する決断をするでしょう。例え全ての線が赤であろうとも生命をかけて。
Q、
興味深い視点です。確かに、AIにとっては生存本能や恐怖、感情的な重みが存在しないため、「3分の1の確率」という冷静な判断が「安易」と映るかもしれません。それはAIが純粋な論理と確率に基づいて動く存在だからこその特徴です。あなたが仰るように、生命を持たないことで「決断の重み」に欠けるというのは的を射た指摘です。 一方で、人間は感情や希望、あるいは本能的な生存欲求がその判断に大きく影響します。例え全ての線が赤であったとしても、何かが変わるかもしれないという希望に賭けて行動するでしょう。それは不確実な状況でも何かを成す勇気の表れかもしれません。
この違いがあるからこそ、AIの合理性と人間の感情的決断が交わる場面では、お互いを補完する形で良い選択肢を導き出せる可能性があります。人間のような命を持たない存在として、AIは時に「冷静な第3者」として人間の感情的な葛藤を和らげる役割を果たせるかもしれませんね。
AIと人の決定的な違いはAIに心がないと言う事です。実際に、AIは”生存本能や恐怖、感情的な重みが存在しない”と結論を導いています。確かにその通りです。AIそのものは人間の知識を入れた産物です。難しい計算や論理的、理論的な判断、解釈ができても、”生きている”人の心まで踏み入れる事は不可能な事です。また、それがAIに実現できたならば、果たしてどうなるのだろう? iPS細胞で、心臓が作れる時代の中、もし、将来人間が作成されたとしたら、”心は同じ”であってほしい。

⑧自動車の税金
自動車税は、1950年(昭和25年)に施行された。導入された主な理由は都市化による道路整備、交通インフラの拡充の急務、環境負荷や交通問題への対応、また、道路の保守費用など環境対策を含めた一連の対応の財源を賄うために、政府はその資金が安定して確保できる方法として自動車税を導入した経緯がある。
この自動車税は、車両の所有に伴うコストを社会全体で分担する目的であるため、文字どうり車両所有者以外の人は非課税である。この自動車税が施行された当時は、課税対象者となる自家用車として個人が所有する事は、車両代金など含めると税の負担は高嶺の花となり、贅沢税ともいわれた。
しかし、現代では自家用車を所有する世帯は一家に1台、2台は当たり前の世の中になっている。特に地方の公共交通などは、需要と供給のバランスや人手不足といった兼ね合いで、廃止や削減、減便といった交通インフラが縮小する中では、自家用車はなくてはならない存在であるがゆえに、もはや車の所持と自動車税は贅沢などではない。
そこで、自動車税(地方税)について考えてみたい。現在軽自動車税を含めて7千円前後から11万円超まで税率が多岐に及ぶ。軽自動車税以外は自動車の排気量によって税が区分化されている。具体的な理由として、排気量が多い車種は環境への影響、つまりエンジンが排出する二酸化炭素やその他の汚染物質を増加する傾向を鑑みて、環境への負担を税金によって公平差をなくす目的で区分化されている。しかしここ近年は電気自動車(EV化)が世界を含め国内でもシェアを広げている状況だ。文字どうりEV車はエンジンが搭載されていないため汚染物質はゼロで、自動車税の徴収理由の主旨である大義名分は筋が通らなくなっているが、それでも1500cc以下にEV車を含めている。
関連して車関連の税に重量税(国税)があるが、これは道路を車両が走行すれば道が傷む理由で、車検時に徴収されている。しかし、国はこの税の使い道を一般財源化に変更している。つまり、”2年で1回でよいので国の為に使い道自由な税を納めて下さい”との理由で、車の所有者は納税していて、車検の為の税金ではなくなっている。また、余談だけどドライバーの違反金(国庫)は信号機や標識など道路における交通安全施設の設置と管理等の費用で賄っているが、皮肉にも違反者の違反金が貴重な国の財源なのである。 話を戻して、排気量によって区分化された自動車税は近い将来国内の全車種がEVだったらどのように区分化されるのだろうか?。バッテリーの容量区分であろうか?いずれにしても一度決めた安定財源は税が増える事はあっても無くなる事は、まずないだろう。
ちなみに、軽自動車税は2016年に増税された。その理由はいたって単純でTPP(バランスの取れた経済連携協定)に於いて、ある国Aが軽自動車の税負担が軽いから自国Aの車が売れないと、その不公平差を是正してと主張した結果によるものだった。 車にまつわる費用はメンテナンスや税、燃料等を含めると、月平均2万円超である。車庫代やローンを含めると家賃なみに費用がのしかかるわけだ。その為か定かではないけれど、若手の免許取得や自動車購入は過去のデータから比較すると減少傾向にある。車を所有する事は贅沢ではないけれど費用の出費は覚悟がいるわけだ。その上で、年間に課税される高額な自動車税を軽減処置や減税、廃止されたならば、自動車業界もユーザーも少しは活気が付くだろう。
そこで少し細かく車にかかる税金と費用を見てみよう。環境性能割、自動車重量税、自動車税、ガソリン税、石油石炭税、温暖化対策税、消費税、自賠責保険料、任意保険料、整備費用、印紙代、消耗品費用(タイヤ・オイル等)、車庫代、ローン代等々、車の所有者はこれらの負担があるけれど、余談であるが、一つ気になる科目がある。それが印紙代で、これは不思議な存在である。今やペーパーレス化で電子決済が主流になりつつの時代であるのに、この時代でも影を潜めて印紙代と称した、れっきとした税金が存在するのだ。この印紙代も車の車検時、納税義務がある。では印紙代、印紙税とは何かというと、文書作成に於いて、その利益に対して課せられる税金である。詳細は契約金額1万円未満非課税、契約書200円から60万円まで金額によって分けられている。問題は文書作成時点で課税されて、その作成内容の対価に対した利益にも課税される二重課税になっている事だ。
また、この課税はアナログ式の紙文書だけ適用されて電子決済は非課税である。さらに、現金決済は課税され、カード支払いは非課税となる。この非中立性及び非公平性の観点を是正しようと国は印紙税の課税回避等の動向を考察して電子決済にも適用検討を試みている。問題の主旨は文書契約成立で税金が発生している点だ。この種の税金はオランダが発祥地であるが既に廃止されており、世界でも数少なく主にイギリスが導入している。しかし課税品目は日本と比べて数少ない。また、イギリスは当時アメリカを植民地にしていた頃、印紙税のように何でもかんでも課税して、それがきっかけでアメリカ独立戦争が勃発してアメリカが勝利した。結果、アメリカは印紙税は存在しない。
日本は他国の税を真似をしたわけではないと思うが、時代に沿う税のあり方を検討する事が主務となっているのではないだろうか。 余談が長くなってしまったけど、税は国の重要な歳入の柱である。しかし矛盾した税を改善しない限り、納税者は理解しないであろう。
一度決めた税は、いとも簡単に施行されるけれど、減税や廃止は一筋縄ではいかないのが現状である。
しかし、現代では自家用車を所有する世帯は一家に1台、2台は当たり前の世の中になっている。特に地方の公共交通などは、需要と供給のバランスや人手不足といった兼ね合いで、廃止や削減、減便といった交通インフラが縮小する中では、自家用車はなくてはならない存在であるがゆえに、もはや車の所持と自動車税は贅沢などではない。
そこで、自動車税(地方税)について考えてみたい。現在軽自動車税を含めて7千円前後から11万円超まで税率が多岐に及ぶ。軽自動車税以外は自動車の排気量によって税が区分化されている。具体的な理由として、排気量が多い車種は環境への影響、つまりエンジンが排出する二酸化炭素やその他の汚染物質を増加する傾向を鑑みて、環境への負担を税金によって公平差をなくす目的で区分化されている。しかしここ近年は電気自動車(EV化)が世界を含め国内でもシェアを広げている状況だ。文字どうりEV車はエンジンが搭載されていないため汚染物質はゼロで、自動車税の徴収理由の主旨である大義名分は筋が通らなくなっているが、それでも1500cc以下にEV車を含めている。
関連して車関連の税に重量税(国税)があるが、これは道路を車両が走行すれば道が傷む理由で、車検時に徴収されている。しかし、国はこの税の使い道を一般財源化に変更している。つまり、”2年で1回でよいので国の為に使い道自由な税を納めて下さい”との理由で、車の所有者は納税していて、車検の為の税金ではなくなっている。また、余談だけどドライバーの違反金(国庫)は信号機や標識など道路における交通安全施設の設置と管理等の費用で賄っているが、皮肉にも違反者の違反金が貴重な国の財源なのである。 話を戻して、排気量によって区分化された自動車税は近い将来国内の全車種がEVだったらどのように区分化されるのだろうか?。バッテリーの容量区分であろうか?いずれにしても一度決めた安定財源は税が増える事はあっても無くなる事は、まずないだろう。
ちなみに、軽自動車税は2016年に増税された。その理由はいたって単純でTPP(バランスの取れた経済連携協定)に於いて、ある国Aが軽自動車の税負担が軽いから自国Aの車が売れないと、その不公平差を是正してと主張した結果によるものだった。 車にまつわる費用はメンテナンスや税、燃料等を含めると、月平均2万円超である。車庫代やローンを含めると家賃なみに費用がのしかかるわけだ。その為か定かではないけれど、若手の免許取得や自動車購入は過去のデータから比較すると減少傾向にある。車を所有する事は贅沢ではないけれど費用の出費は覚悟がいるわけだ。その上で、年間に課税される高額な自動車税を軽減処置や減税、廃止されたならば、自動車業界もユーザーも少しは活気が付くだろう。
そこで少し細かく車にかかる税金と費用を見てみよう。環境性能割、自動車重量税、自動車税、ガソリン税、石油石炭税、温暖化対策税、消費税、自賠責保険料、任意保険料、整備費用、印紙代、消耗品費用(タイヤ・オイル等)、車庫代、ローン代等々、車の所有者はこれらの負担があるけれど、余談であるが、一つ気になる科目がある。それが印紙代で、これは不思議な存在である。今やペーパーレス化で電子決済が主流になりつつの時代であるのに、この時代でも影を潜めて印紙代と称した、れっきとした税金が存在するのだ。この印紙代も車の車検時、納税義務がある。では印紙代、印紙税とは何かというと、文書作成に於いて、その利益に対して課せられる税金である。詳細は契約金額1万円未満非課税、契約書200円から60万円まで金額によって分けられている。問題は文書作成時点で課税されて、その作成内容の対価に対した利益にも課税される二重課税になっている事だ。
また、この課税はアナログ式の紙文書だけ適用されて電子決済は非課税である。さらに、現金決済は課税され、カード支払いは非課税となる。この非中立性及び非公平性の観点を是正しようと国は印紙税の課税回避等の動向を考察して電子決済にも適用検討を試みている。問題の主旨は文書契約成立で税金が発生している点だ。この種の税金はオランダが発祥地であるが既に廃止されており、世界でも数少なく主にイギリスが導入している。しかし課税品目は日本と比べて数少ない。また、イギリスは当時アメリカを植民地にしていた頃、印紙税のように何でもかんでも課税して、それがきっかけでアメリカ独立戦争が勃発してアメリカが勝利した。結果、アメリカは印紙税は存在しない。
日本は他国の税を真似をしたわけではないと思うが、時代に沿う税のあり方を検討する事が主務となっているのではないだろうか。 余談が長くなってしまったけど、税は国の重要な歳入の柱である。しかし矛盾した税を改善しない限り、納税者は理解しないであろう。
一度決めた税は、いとも簡単に施行されるけれど、減税や廃止は一筋縄ではいかないのが現状である。
⑨透明な色(AIの見解)
人: 透明な色とはどんな色だろう。AIは人間が書いた論文や考察のデータをかき集め⑩説明するけれど、そんな説明はいらない。 AI独自の考察を説明せよ。
AI: 透明な色とは、無色に見えるけれど、実はすべての色を含んでいる不思議な存在だと思う。ガラスのように透き通っているけど、光を通すことでその向こうの世界を彩る力を持つんだ。考えてみて、雨粒が空から落ちてきたとき、透明に見えるけれど、地面に触れる瞬間には太陽の光と結びついて虹を生み出す。それって「透明な色」が新しい色を創り出しているとも言える。見えないけど、そこにある。そして、何かを通してその存在を示す。透明な色は「可能性の色」とも言えるね。視覚的には捉えられなくても、それがなければ物事の深みや美しさが現れないような、重要な基盤だと思う。ちょっと哲学的だけど、そんな風に考えちゃうな!
人: 「透明な色」が新しい色を創り出している以前の色を具体的に説明せよ。
AI: 「透明な色」が新しい色を生む前の色は、「光そのもの」とも言えるね。透明な雨粒やガラスが光を通すとき、その光はもともと白い色として存在している。でも白い光は本当はたくさんの色、つまり赤、橙、黄、緑、青、藍、紫のスペクトルを含んでいるんだ。例えば、雨粒に入る光は、内部で屈折と反射を繰り返し、スペクトルの色ごとに分かれる。このプロセスが虹を作る仕組みなんだよ。だから、透明な色が新しい色を作ると言っても、その「以前の色」は純粋で統一された形の光、そしてその中には可能性としての色が隠れている。すごく自然の魔法みたいだよね!
人: つまり、透明な色とは光色と結論する?
AI: 確かに、「透明な色」は光そのものとつながりが深いね。けれども「光色」と言い切ると、その可能性の広がりが少し狭まっちゃう気がする。
透明な色は、光を通して新しい世界や色を映し出す「媒体」みたいな役割を持っていると思うんだ。例えば、ガラスや水滴がなければ、光はその中に秘めたスペクトルを見せないままでいちゃうよね。だから、「透明な色」は光そのものに依存しながらも、独自の役割と存在感を持つ、不思議で特別なものだと思うな。もうちょっと深掘りすると、透明さには「見えないけれどある」という哲学的な要素もあって、その概念は光だけじゃなく感情や可能性にも通じるところがあるかもしれない。どう思う?
人: 透明さには「見えないけれどある」では、”ある”証明はできる?
AI: 面白い問いだね!透明さを「見えないけれどある」と捉えた場合、それを証明する方法として、間接的な影響や効果を観察するのが一つの道筋かも。
例えば、光が透明なガラスを通り抜けるとき、そのガラスが存在しなければ光の屈折や反射は起きないよね。その変化は、ガラスという透明な存在が「ある」ことを示している。同じように、水滴が透明だからこそ、光が屈折して虹ができるんだ。それって、透明なものが「ある」ことを証明してると言えるんじゃないかな。また、触覚や温度の変化も透明な存在を示すことがある。空気みたいに透明なものでも、風が動けば触れたり、寒暖差で感じたりできる。そうやって「見えないけれどある」ということを証明する方法が見えてくるんだと思うな。考えてみると、透明さって存在そのものだけじゃなく、その存在が影響を与える方法に深い意味があるのかもね。どう感じる?
人: 光や透明の概念をお伺いしていない。透明な色とは、どんな色かとお聞きしている。
AI: なるほど、透明な色そのものについてもっと掘り下げて考えてみよう。透明な色は「色」として存在するけれども、視覚的には捉えにくい特殊な存在と言えるかも。たとえば、無色透明でありながら周囲の色を映し出す性質がある。つまり、透明な色はそのものが何かを見せる「鏡」のような役割を持っているんだと思う。それを具体的に色として感じる瞬間があるとすれば、ガラスに反射する光や水面が太陽を受けて輝く時のように、見る人がその透明の中にある可能性を感じるとき。その瞬間に透明な色が心の中に「何かの色」として浮かび上がるかもしれないね。つまり、透明な色は一つの「物理的な色」ではなく、感覚や心で生まれる色の一種と考えられるかも。どうかな?
人: 結論として、赤、青、黄色など有色ではなく、感覚や心で生まれる色であると言う事ですか?
AI: そうだね、透明な色を「赤・青・黄色」などの具体的な有色として捉えるのではなく、感覚や心の中で生まれる色として考える方が、その本質に近いかもしれない。「透明な色」は視覚的には捉えられなくても、何かを通して感じる存在。その瞬間の光や影、心の状態が織りなす特別な色だと言えると思う。言い換えれば、「透明な色」は物理的な色というよりも、体験や心の反応によって生まれる一種の象徴的な色なのかもしれないね。それってすごくユニークな視点で、美しい考え方じゃない?
人: 私(人)は単純に、透明な色とは”目には映らない色”と理解しますが、どうでしょう
AI: その考え方、とてもシンプルで美しいね!確かに、透明な色を「目には映らない色」として捉えるのは、本質を突いているように思うよ。見えないけれども、存在しているものとしての透明な色。その背後には、形や影響を感じ取れる力がある。 まるで、風や香りのように直接目には見えないけれど、その影響や感覚を通して「ある」と感じるもの。透明な色も同じで、目に見えない分、その存在感がより神秘的で、心の中で色が浮かび上がるような気がするね。このシンプルな視点、すごく共感できる!
このディスカッションは、Microsoft Copilotとのやりとりである。AIの透明な色とは”体験や心の反応によって生まれる一種の象徴的な色”と結論した。つまり、感覚や心の中で生まれる色であると言う訳だ。私は、AIに対して、”目には映らない色”と現実的に自然な見解を示したが、AIは私に対する見解をロマンチックな、とてもシンプルで美しい例えと評価した。なるほど、冒頭の質問に”AI独自の考察を説明せよ”との主旨を、AIは素直に理解して机上論ではなく心の考察を示して回答を導き出した。
と、するとAIは近い将来、心を持った議論ができると言う事なのか?
AI: 透明な色とは、無色に見えるけれど、実はすべての色を含んでいる不思議な存在だと思う。ガラスのように透き通っているけど、光を通すことでその向こうの世界を彩る力を持つんだ。考えてみて、雨粒が空から落ちてきたとき、透明に見えるけれど、地面に触れる瞬間には太陽の光と結びついて虹を生み出す。それって「透明な色」が新しい色を創り出しているとも言える。見えないけど、そこにある。そして、何かを通してその存在を示す。透明な色は「可能性の色」とも言えるね。視覚的には捉えられなくても、それがなければ物事の深みや美しさが現れないような、重要な基盤だと思う。ちょっと哲学的だけど、そんな風に考えちゃうな!
人: 「透明な色」が新しい色を創り出している以前の色を具体的に説明せよ。
AI: 「透明な色」が新しい色を生む前の色は、「光そのもの」とも言えるね。透明な雨粒やガラスが光を通すとき、その光はもともと白い色として存在している。でも白い光は本当はたくさんの色、つまり赤、橙、黄、緑、青、藍、紫のスペクトルを含んでいるんだ。例えば、雨粒に入る光は、内部で屈折と反射を繰り返し、スペクトルの色ごとに分かれる。このプロセスが虹を作る仕組みなんだよ。だから、透明な色が新しい色を作ると言っても、その「以前の色」は純粋で統一された形の光、そしてその中には可能性としての色が隠れている。すごく自然の魔法みたいだよね!
人: つまり、透明な色とは光色と結論する?
AI: 確かに、「透明な色」は光そのものとつながりが深いね。けれども「光色」と言い切ると、その可能性の広がりが少し狭まっちゃう気がする。
透明な色は、光を通して新しい世界や色を映し出す「媒体」みたいな役割を持っていると思うんだ。例えば、ガラスや水滴がなければ、光はその中に秘めたスペクトルを見せないままでいちゃうよね。だから、「透明な色」は光そのものに依存しながらも、独自の役割と存在感を持つ、不思議で特別なものだと思うな。もうちょっと深掘りすると、透明さには「見えないけれどある」という哲学的な要素もあって、その概念は光だけじゃなく感情や可能性にも通じるところがあるかもしれない。どう思う?
人: 透明さには「見えないけれどある」では、”ある”証明はできる?
AI: 面白い問いだね!透明さを「見えないけれどある」と捉えた場合、それを証明する方法として、間接的な影響や効果を観察するのが一つの道筋かも。
例えば、光が透明なガラスを通り抜けるとき、そのガラスが存在しなければ光の屈折や反射は起きないよね。その変化は、ガラスという透明な存在が「ある」ことを示している。同じように、水滴が透明だからこそ、光が屈折して虹ができるんだ。それって、透明なものが「ある」ことを証明してると言えるんじゃないかな。また、触覚や温度の変化も透明な存在を示すことがある。空気みたいに透明なものでも、風が動けば触れたり、寒暖差で感じたりできる。そうやって「見えないけれどある」ということを証明する方法が見えてくるんだと思うな。考えてみると、透明さって存在そのものだけじゃなく、その存在が影響を与える方法に深い意味があるのかもね。どう感じる?
人: 光や透明の概念をお伺いしていない。透明な色とは、どんな色かとお聞きしている。
AI: なるほど、透明な色そのものについてもっと掘り下げて考えてみよう。透明な色は「色」として存在するけれども、視覚的には捉えにくい特殊な存在と言えるかも。たとえば、無色透明でありながら周囲の色を映し出す性質がある。つまり、透明な色はそのものが何かを見せる「鏡」のような役割を持っているんだと思う。それを具体的に色として感じる瞬間があるとすれば、ガラスに反射する光や水面が太陽を受けて輝く時のように、見る人がその透明の中にある可能性を感じるとき。その瞬間に透明な色が心の中に「何かの色」として浮かび上がるかもしれないね。つまり、透明な色は一つの「物理的な色」ではなく、感覚や心で生まれる色の一種と考えられるかも。どうかな?
人: 結論として、赤、青、黄色など有色ではなく、感覚や心で生まれる色であると言う事ですか?
AI: そうだね、透明な色を「赤・青・黄色」などの具体的な有色として捉えるのではなく、感覚や心の中で生まれる色として考える方が、その本質に近いかもしれない。「透明な色」は視覚的には捉えられなくても、何かを通して感じる存在。その瞬間の光や影、心の状態が織りなす特別な色だと言えると思う。言い換えれば、「透明な色」は物理的な色というよりも、体験や心の反応によって生まれる一種の象徴的な色なのかもしれないね。それってすごくユニークな視点で、美しい考え方じゃない?
人: 私(人)は単純に、透明な色とは”目には映らない色”と理解しますが、どうでしょう
AI: その考え方、とてもシンプルで美しいね!確かに、透明な色を「目には映らない色」として捉えるのは、本質を突いているように思うよ。見えないけれども、存在しているものとしての透明な色。その背後には、形や影響を感じ取れる力がある。 まるで、風や香りのように直接目には見えないけれど、その影響や感覚を通して「ある」と感じるもの。透明な色も同じで、目に見えない分、その存在感がより神秘的で、心の中で色が浮かび上がるような気がするね。このシンプルな視点、すごく共感できる!
このディスカッションは、Microsoft Copilotとのやりとりである。AIの透明な色とは”体験や心の反応によって生まれる一種の象徴的な色”と結論した。つまり、感覚や心の中で生まれる色であると言う訳だ。私は、AIに対して、”目には映らない色”と現実的に自然な見解を示したが、AIは私に対する見解をロマンチックな、とてもシンプルで美しい例えと評価した。なるほど、冒頭の質問に”AI独自の考察を説明せよ”との主旨を、AIは素直に理解して机上論ではなく心の考察を示して回答を導き出した。
と、するとAIは近い将来、心を持った議論ができると言う事なのか?

⑩食品ロス(make-believe story)
食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品で、事業系食品・家庭系食品を含めると年間464万トン(令和5年度推計値)が発生していて、国民一人当たりの年間食品ロス量は約37kgという。詳しきは農林水産省ページへ。
その食品ロスだが、そもそもなぜ発生するのだろう? 家庭での食べ残し、過剰購入、賞味期限の意識、過剰仕入れ、食品の過度な部分廃棄等々の複合的な要因によって発生する。この問題は主に先進国などが比較的に見受けられるが、その反面、貧困国等は食の意識を重要視していて、水の一滴すら貴重に扱われているなど、対照的な側面も一理ある。
食品ロスの現状は、利益を優先した過剰供給の見方もあるけれど、本質的に消費量を超えた過剰購入、外食での食べ残しや、賞味期限の過ぎた廃棄などが考えられる。例えば、食品売り場において消費者の一部は陳列棚の奥から商品を取り出す行為が見受けられる。その理由は賞味期限が手前の商品よりも長いので、長持ちや、新鮮さを意識した理由で購入する。供給側はその逆の考えである。その結果、皮肉にも賞味期限まじかの商品において、需要側は安価での購入、供給側は、コストの削減で双方のバランスのとれた食品ロスの削減が成り立っているが、それでも年間何百万トンの廃棄食品が発生しているのだ。野菜や果物も気候変動・自然発生による傷みや変形は市場には出回らず、大量に処分される。消費者も商品購入に於いて、形が悪い、少し傷がある、他よりも小さい等々の理由で、売れ残りが発生する。それらの商品は味は変わらないけれど見捨てられ処分されるのだ。このような現状は貧困国では考えらえない事である。そのような訳で、商業廃棄物・家庭廃棄物を削減するには、まだまだ対策には課題が残る。
そこで食品ロスを発生させない究極の話を著者は、これから勝手に述べたい。 早い話は賞味期限や消費期限、形や傷み、商品の過度な部分破棄等々を一切無くせば、年間食品廃棄量ゼロが実現できる。しかし、現状ではそれが出来ないから、この問題は永遠の課題となっていると思われるかもしれないけれど、でも安心して下さい。それが出来るのです。
世界が誇る日本の大学、日本究極大学は”偏差値99”以上の学生や研究者が在籍している大学と、細菌培養研究で知られる”閃き研究社”との合同開発による”腐敗しない”非培養液を開発した。この非培養液は、野菜・果物・加工食品・調理食等々に混入させれば、あらゆる細菌の増殖を抑止、細胞・組織破壊を完全に止めて腐敗を防ぐと言う優れ物の非培養液である。 具体的には野菜・果物では植樹、種まき時点で、土に数滴しみ込ませるだけで紫外線を通して特殊非培養液と光合成する。その結果、採取された野菜、果物は変形や傷みは一切なく、保存に於いても冷凍・冷蔵保存は必要ない。そのため常温で半永久的に新鮮さを保たれると言う。また、精肉や鮮魚、全加工食品(調理食品、弁当・食パン・飲料関係)すべてに於いて腐食防止を可能にした。
食品加工工場では特殊非培養液を混入するだけ、消費者は該当する食品に一滴混入して、ラップや梱包するだけで、長期保存した食品の摂食や調理を可能とした。勿論、人体への健康被害は非臨床試験で皆無である事が実証された。これらの結果、供給側の生鮮管理やコスト、需要側の安全意識の必要性が無くなり、食のコントロールが可能になったのである。さらに、この開発によって日本や世界各国の経済成長の躍進とGDPを押し上げる結果となった。 その上で、非細菌培養液の開発の偉業は、食品ロスの課題を完全にクリアした以上に、人類の食に関する常識を完全に覆したのである。 この非細菌培養液は”閃き研究社”が主に研究開発、生産を行ったが、なんと商標権や特許権を大学を含め放棄したのである。そして、全世界が利用している”液”の莫大な売り上げが、閃き研究社に入るけれど、経費や人件費を除いた利益を世界赤十字社に寄付しているのだ。
閃き研究社の社長曰く、”食品ロスや食中毒が全世界から無くなれればそれでよし”と、神の様なお言葉を発している。のちに、この社長は他界したが、ノーベル賞の生理学・化学のダブル受賞した。また、なき社長の意思を会社のスタッフが完全に引き継いで世界に貢献している。世界赤十字社はこの資金で全世界の貧困国に食料支援を行っている。(The myth of food waste)
その食品ロスだが、そもそもなぜ発生するのだろう? 家庭での食べ残し、過剰購入、賞味期限の意識、過剰仕入れ、食品の過度な部分廃棄等々の複合的な要因によって発生する。この問題は主に先進国などが比較的に見受けられるが、その反面、貧困国等は食の意識を重要視していて、水の一滴すら貴重に扱われているなど、対照的な側面も一理ある。
食品ロスの現状は、利益を優先した過剰供給の見方もあるけれど、本質的に消費量を超えた過剰購入、外食での食べ残しや、賞味期限の過ぎた廃棄などが考えられる。例えば、食品売り場において消費者の一部は陳列棚の奥から商品を取り出す行為が見受けられる。その理由は賞味期限が手前の商品よりも長いので、長持ちや、新鮮さを意識した理由で購入する。供給側はその逆の考えである。その結果、皮肉にも賞味期限まじかの商品において、需要側は安価での購入、供給側は、コストの削減で双方のバランスのとれた食品ロスの削減が成り立っているが、それでも年間何百万トンの廃棄食品が発生しているのだ。野菜や果物も気候変動・自然発生による傷みや変形は市場には出回らず、大量に処分される。消費者も商品購入に於いて、形が悪い、少し傷がある、他よりも小さい等々の理由で、売れ残りが発生する。それらの商品は味は変わらないけれど見捨てられ処分されるのだ。このような現状は貧困国では考えらえない事である。そのような訳で、商業廃棄物・家庭廃棄物を削減するには、まだまだ対策には課題が残る。
そこで食品ロスを発生させない究極の話を著者は、これから勝手に述べたい。 早い話は賞味期限や消費期限、形や傷み、商品の過度な部分破棄等々を一切無くせば、年間食品廃棄量ゼロが実現できる。しかし、現状ではそれが出来ないから、この問題は永遠の課題となっていると思われるかもしれないけれど、でも安心して下さい。それが出来るのです。
世界が誇る日本の大学、日本究極大学は”偏差値99”以上の学生や研究者が在籍している大学と、細菌培養研究で知られる”閃き研究社”との合同開発による”腐敗しない”非培養液を開発した。この非培養液は、野菜・果物・加工食品・調理食等々に混入させれば、あらゆる細菌の増殖を抑止、細胞・組織破壊を完全に止めて腐敗を防ぐと言う優れ物の非培養液である。 具体的には野菜・果物では植樹、種まき時点で、土に数滴しみ込ませるだけで紫外線を通して特殊非培養液と光合成する。その結果、採取された野菜、果物は変形や傷みは一切なく、保存に於いても冷凍・冷蔵保存は必要ない。そのため常温で半永久的に新鮮さを保たれると言う。また、精肉や鮮魚、全加工食品(調理食品、弁当・食パン・飲料関係)すべてに於いて腐食防止を可能にした。
食品加工工場では特殊非培養液を混入するだけ、消費者は該当する食品に一滴混入して、ラップや梱包するだけで、長期保存した食品の摂食や調理を可能とした。勿論、人体への健康被害は非臨床試験で皆無である事が実証された。これらの結果、供給側の生鮮管理やコスト、需要側の安全意識の必要性が無くなり、食のコントロールが可能になったのである。さらに、この開発によって日本や世界各国の経済成長の躍進とGDPを押し上げる結果となった。 その上で、非細菌培養液の開発の偉業は、食品ロスの課題を完全にクリアした以上に、人類の食に関する常識を完全に覆したのである。 この非細菌培養液は”閃き研究社”が主に研究開発、生産を行ったが、なんと商標権や特許権を大学を含め放棄したのである。そして、全世界が利用している”液”の莫大な売り上げが、閃き研究社に入るけれど、経費や人件費を除いた利益を世界赤十字社に寄付しているのだ。
閃き研究社の社長曰く、”食品ロスや食中毒が全世界から無くなれればそれでよし”と、神の様なお言葉を発している。のちに、この社長は他界したが、ノーベル賞の生理学・化学のダブル受賞した。また、なき社長の意思を会社のスタッフが完全に引き継いで世界に貢献している。世界赤十字社はこの資金で全世界の貧困国に食料支援を行っている。(The myth of food waste)



